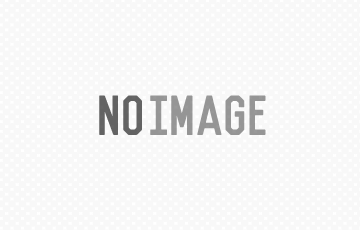タマゴタケが姿を消し、テングタケが群生していた
先週に引き続き、ラクヨウを探しに山へ入っていた。結論からいうと、道南方面のラクヨウは時期尚早であると思う。勿論、場所や標高によりラクヨウの発生は左右されるので、あくまでも僕が行く界隈という意味である。
はじめにお断りしておくけど、テングタケは毒キノコであり、当然ながら食べる事は出来ない。ただ、被写体としてはなかなか面白いキノコであると思う。それと本来のテングタケは広葉樹林に生えるらしい。ラクヨウ狙いなので、訪れたのは針葉樹林である。この針葉樹林に生えるテングタケは、イボテングタケという別種とのことだ。しかし、文中ではテングタケと記載している。

ツボ(根元の白い繭状のもの)から頭を出したばかりのテングタケ

柄の部分が伸びてきたテングタケ

傘の開く前のテングタケ

傘が開いたテングタケ

見事なテングタケだった。大きな個体は直径20cm近い。

これはタマゴタケ 美味しいキノコだが、テングタケ科は毒キノコが多く、確実に判断出来ない限りは採取は不可である。
タマゴタケの柄には本来、薄茶の模様(だんだら模様)がついているのが特徴であるらしい。しかし、個体によっては全く模様がなく、黄色い柄であるものがある。調べてみると、セイヨウタマゴタケという種は模様がないそうである。ただ、日本固有の種として別種ではないのかという意見もあるそうで、もしかすると、イボテングタケの様に亜種のように区別されるのかもしれない。
タマゴタケと似ていると言われるのが、ベニテングタケとタマゴタケモドキやタマゴテングタケ。ベニテングタケの場合は柄が白い事と若い個体は傘に白いイボがある筈だ。タマゴテングタケやタマゴタケモドキは実物を見たことがないので、色合いで判断出来るのかは判らない。ただ、タマゴテングタケやタマゴタケモドキは、タマゴタケほど明確な条線はないようだ。また、タマゴタケはツバも黄色いのに対し、白いツバは付くらしい。
何れにしても、紛らわしいキノコは採取しないのが鉄則であろう。

柄のだんだら模様、傘の条線、黄色い柄とオレンジ色の傘 典型的なタマゴタケ

朽ちかけているブナハリタケ 好きな人は採取するようだが、僕は独特の癖が苦手だ

恐らくスギタケモドキ 柄にもトゲがあるので、ヌメリスギタケモドキではない

こちらはヌメリスギタケモドキ

ホウキタケか?

帰り際にみつけたツユクサ